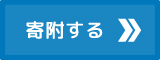法文学部 石田 新さん(4年生)
令和6年度 グローバルチャレンジ奨学金受給者
<食の歴史ゼミモンゴル研修>
研修では,古代から近代に至るあらゆる遺物が多数展示されている「チンギスハーン国立博物館」,チベット仏教に関する美術品を扱った「ザナバザル美術館」,広大な敷地面積と巨大な観音像を有する「ガンダン・テクツェンリン寺」,そして20世紀から21世紀に至るモンゴルの美術品を収蔵した「モンゴル近代美術館」といった施設を訪れた。展示物の多くが,日本では目にすることのできない貴重な一次資料であり,また各展示物について詳細な説明が付されていたため,歴史学を専攻する身としては,非常に充実した時間を過ごすことができた。加えて,モンゴル考古学を専攻している坂川先生も現地で同行してくださったため,先生によるガイドと解説も併せて楽しむことができた。また,ウランバートル市内には,至る所にモンゴルの歴史に因んだ人物の銅像が建てられており,紙幣であるトゥグルグにもチンギスハーンの肖像が描かれていた。これらのことからも,モンゴルの歴史的文化が生活の中に根差したものであるということを伺い知ることができた。
私にとって人生初めての海外旅行であった今回のモンゴル研修を通じて,これまで私自身がどれだけ日本語に頼った生活を送ってきたのかということを痛感した。モンゴル国内で一般的に使用されているモンゴル語の文字は,ロシア語に用いるキリル文字とөとүの二つの母音字を足したもので表記される。当然であるが,アルファベット表記とは異なるため,モンゴル語に精通していなければ発音することが難しく,この点はコミュニケーションにおいても同様である。それゆえに,英語を多少知っている程度の語学力では到底太刀打ちすることができず,研修中も,坂川先生をはじめ,日本語の話せる現地の方に通訳をしてもらったり,ジェスチャーや翻訳アプリを駆使したりして何とか意思疎通を図った。このこととは対照的に,意外だったのは,現地に住む方の中には日本語を話せる人が結構いたことである。特に,ある飲食店で私たちが食べ物を注文するのに苦戦していると,近くに居たモンゴル人の方が,代わりに通訳をして助けて下さったのがとても印象に残っている。また,自分たちの拙い英語を何とかして聞き取ろうとしたり,困っている時にはそっと手を差し伸べてくれたりと,たとえ言語が違えども,人に対して親切にしようとする精神は世界共通なのだと改めて実感した。
以上,今回の海外研修を通じて,モンゴル人の生活文化の基底をなす“歴史と伝統”及び海外における言語の重要性について,再認識することができた。
今回の海外研修の内容については,今後,写真や動画等を編集してゼミ紹介の際に活用するとともに,『歴史学通信』などの成果報告書に,研修の感想を寄稿することによって,より一層海外研修に対する知識・理解を広めていき,研修への興味・関心を促していきたいと考えている。また,現地でも実食したモンゴルの伝統料理であるホーショール(モンゴルの揚げ餃子)を作り,学園祭で売る予定である。このように,モンゴルでの体験を積極的に発信していき,海外研修の魅力を少しでも多くの人に伝えていきたいと思う。
加えて,個人的な課題として,語学学習が挙げられる。実際,英語を喋れるかどうかで,海外渡航に対するハードルはかなり変わってくるように思われるため,まずは英語力を向上させていきたい。モンゴルで私たちが困っている時に,日本語で話しかけてくれたモンゴル人の方のように,海外の観光客が日本で困っている際には,英語を使って,彼らを助けられるような人になりたいと今回の研修を通して改めて思った。このことをモチベーションにしながら日々の英語学習に励んでいきたいと思う。
自然科学研究科 *****さん(2年生)
令和6年度 グローバルチャレンジ奨学金受給者
<インド工科大学ハイデラバード校(IITH)との交換留学>
研究室に所属し研究を行った。ボランティアに唾液サンプルを提供してもらい,IITHのラマン顕微鏡を使用して唾液のラマンスペクトルを測定した。島根大学で使用している機器とは異なるため,機器の使用方法から学ぶ必要があった。実験を行う上で研究室の方がアドバイスをしてくださり,より多くの方と研究について議論することができたため,自身の研究の課題点に着目することができた。
また学部でカンファレンスが開催され研究室の方の発表を聞く機会があった。インドの学生と繋がりを持つことができ,国際的なネットワークを広げることができた。また同年代の方とお話しし,インドの文化や習慣を知った。日本とは異なる環境での生活であり適応する必要があったため,トラブルが生じても周りの方を頼りながら対応するなど柔軟性が身についた。
一か月間の短い研修だったが,充実した日々を過ごすことができた。文化も言語も全く異なる環境での生活を通して,異文化理解が深まった。トラブルにも柔軟に対応することができ,自身の成長に繋がったと感じる。研究だけでなく,現地での人との繋がりを深めることができ,国際的な視野を広げることができた。
IITHで私のような日本の学生や留学生を見かけることが非常に少なかった。そのため私のインドでの経験を研究室の皆や大学の方に伝え,インドへ留学したいと思ってもらえる活動がしたい。
異文化に直接触れたことで戸惑いも生じたが,様々な価値観があることを知れた。これから社会に出た際,より多くのバックグラウンドの方と関わる機会があるため,お互いへの尊重を心掛けたい。また英語での会話で何度も聞き返し,うまく言葉にできないことが多くあった。自身の語学力をより高め,多くの方とコミュニケーションが取れるようになりたいと感じた。
医学部 大平 幸子さん(4年生)
令和6年度 グローバルチャレンジ奨学金受給者
<カンボジア研修>
NPO法人の日本語学校に訪れ,日本語の需要は近年下がっており,円安のこともあり日本語を覚えてもお金にならないとカンボジア人が感じていることを知った。この学校ではプノンペン以外に農村の方で教育機関を立ち上げようと活動されている。無償で医療が届かない農村地域での医療活動JapanHeartこども医療センターを見学した。日本からボランティア医師が派遣され,現地で小児がん患者や大人の患者まで幅広く診ていた。医療資源は限られており,CTやMRIなどの画像診断は市内まで車で行かないといけない。こども医療センターの目標は生まれる場所によって子どもの生命に差がある,それを改善し小児がん患者の生存率を上げると話されていた。カンボジア唯一の国立医学部に訪問し,カンボジア大学を島根大学医学部の海外研修Bプログラムに追加することを目的に訪問した。カンボジアでは総合診療医と専門医でなるために必要な費用や道のりが日本と大きく異なった。Sunrise Japan Hospitalは有償で富裕層のカンボジア患者向けの医療ビジネスを行う病院だった。ドクターヘリは導入できていないため,富裕層のカンボジア人のプライベートヘリを借りて医療活動をする計画をされていた。カンボジア救急救命隊RRC711部隊の見学もした。日本から期限切れだが十分使用可能な消防車や救急車が多数寄付されていた。災害時には派遣されて軍の救助活動を行い,通常は日本と同じく救急救命隊として活動するそうだと知った。
今回のカンボジアの初めての訪問で歴史や医療についてふれ,もっと多くの人に知ってほしいと思った。そこでこの一週間の研修内容を発表したり,同伴させていただいた大学の先生が計画しているカンボジアのスタディツアー・海外研修の立ち上げに援助として加わり多くの学生がカンボジアに行きやすくしていきたい。また自分自身,将来国際医療支援を行いたいと漠然としか考えていなかったが,今回の研修を終えてどのような形で医療支援に携わるのか,長期で滞在するのか災害時など緊急時に援助として加わるのか,ボランティア派遣でくる医師の調整をするロジスティクスとして携わるか,いろんな選択肢があることを知ったので今後の将来像を考えていきたい。
教育学部 岡本 真萌さん(2年生)
令和6年度 グローバルチャレンジ奨学金受給者
<フィンランド教育関係視察研修>
今回の研修を通して,フィンランド教育はとても自由であると思っていたが,授業や教室に多少違いはありながらも日本とそこまで変わらないと感じた。日本とフィンランドで大きく違うのは,支援体制や社会の仕組みであると学んだ。特に,日本では教員不足や働き方といった課題があるが,フィンランドでは1クラスに合わせて3~4人の教員がおり,授業も早く終わることがあるため,教員が学校に残るということはない。また,フィンランドと言えば税率の高さが有名であるが,それでもなお幸福度が高いのは,政府がどのように税金を使っているのかをきちんと国民・市民に提示しており,教育支援も生前から成人まで長期にわたってサポートされるからだと考えた。研修を通して特に驚いたのは,図書館の存在であった。図書館と聞くと,静かで本を借りる所というイメージを持ち,使用頻度は低いだろう。しかしフィンランドは,タンペレ市内だけでも14か所の図書館があり,図書館は静かな所ではなく,自由に誰でも無料で利用することができ,様々な目的を満たすサービスを提供し,ウェルビーイングを与える場としての役割を果たしていた。平日の午後でも夜でも老若男女問わず多くの人が利用しており,本を読む人,ゲームをする人,楽器を練習する人,軽食を食べる人など私たちがイメージする図書館とは全く異なる姿だった。このような場所が身近にあることは,安心した空間の中で勉強や仕事に励んだり,友達と遊んだり,趣味に没頭したりすることができ,結果として高い学力や高い幸福度につながると学習した。
今回改めて感じた日本の教育や社会の良さを生かしながら,子どもだけではなく,全ての人がウェルビーイングを感じる場づくりに努めたい。特に,今年は教育実習があるため,どのような空間や環境づくりをするのかをフィンランドでの学びと日本の今の両方を考えて,実践していきたい。また,教育で抱える問題は教育現場を変えるだけではだめだと感じた。だからこそ,社会の働き方であったり,図書館や公民館などの社会教育施設のあり方を見つめ直し,考えるだけはでなく,それを発信したり行動したりしていくことが大切であると思った。そのためにも,今回印象深かった図書館や教室の環境,働き方などについてもっと情報を集め,選択の幅を広げることができたら良いと感じた。
総合理工学部 須田 珠那さん(1年生)
令和5年度 グローバルチャレンジ奨学金受給者
今回のタイチェンマイ大学サマースクールに参加して学んだことは2つある。
1つ目に,英語のコミュニケーションツールとしての重要性である。義務教育が開始する小学生から私たちは英語に触れ,学ぶ。高校を含めて約6年間英語を学ぶにも関わらず,日本人は英語が苦手だとよく言われる。私も英語,特にスピーキングに苦手があった。しかし今回の研修を通して,日本人は英語が苦手だといわれる理由とそれに対する対処法を見つけた。タイで2週間生活をする中で様々な人に出会った。タイ人はタイ語が第一言語であり英語を全員が流暢に話せるわけではない。だが,間違っている英語だとしても失敗を恐れず,日本人の私と交流をし,理解しあうために英語を使うバディーやホテルのスタッフの方の姿からは言語は意思疎通のためにあるという本来の存在意義を改めて認識した。英語には「正しい」文法が存在し,正しく英語を話せるように学習を進める。そこにはメリットもあるが,正しさを求めるあまり気持ちを表現することが大切なコミュニケーションの場でさえも間違いを恐れ,結局は何も話せなくなってしまうというデメリットがあると思った。研修を終え,私は今までよりも英語を話すことに対する恐怖心が薄れた。これはコミュニケーションツールとしての重要性を認識し,間違えを許容するようになれたからだ。今のような文法や読解がメインの英語教育に加え,いろいろな国籍,文化を持つ人の生きた英語を学ぶことが大切になっていくと思った。
2つ目に,タイの文化や歴史についてである。研修では午前は英語の学習,午後は主にタイの歴史や自然に触れる野外活動を行った。私が最も記憶に残ったのは水についての講義とそれに関する野外活動である。水は私たちにとって大切である。チェンマイの川は人間の行動,生活によって汚濁が目立っている。きれいな川を取り戻すためにどのような活動が行われているかを学んだ。川をきれいにするために周辺に植物を植えたり,周辺住民によって川からごみを取り除いたりする作業が行われたそうだ。この活動を通して,人と技術のどちらが欠けても課題解決にはつながらないということを実感した。世界には様々な問題があるがそれらを解決するためそのようなことを重視していきたい。
今回の研修では上記の通り,英語のコミュニケーションツールとしての重要性とタイの文化や歴史について学んだ。これらのことを生かしてこれから取り組みたいことが2つある。まずは,英語活用能力の向上である。研修の中でもっと英語を自由に操り,コミュニケーションを楽しくとれるようになりたいという気持ちが大きくなった。読み書きはもちろん大切だが,今後は教養科目で発展的なスピーキングをメインとする授業に積極的に参加することで英語を伸ばしていきたいと思う。次に島大アンバサダーの活動についてである。スキルアップセミナーや海外からの訪問者への学校案内などに積極的に参加していきたいと思っている。
医学部 *****さん(3年生)
令和5年度 グローバルチャレンジ奨学金受給者
最初の2日間は Cebu Province Hospital を見学させていただきました。病院見学をさせていただいた他手術の見学,分娩室,緊急救命室,入院患者さんの回診,動物咬傷の外来,入院患者の朝の病棟の回診を見学させていただき一部手伝わせていただきました。この Cebu Province Hospital には病室はもちろん個室はなく,担当医(private doctor)がいない限りは冷房のある部屋には入れず,大きな部屋に複数ベッドを置き点滴は天井からぶら下がり扇風機を持参しており,酸素マスクもなく患者の家族が手動で袋を押しながら空気を送るという方法であり,病院内にはMRI,CTはなくX線しかないなど医療設備が少なかったです。カルテは全て紙媒体であり手書きで記録を全て取っていました。このように日本の整った医療,医療施設からは程遠くその違いに驚かされました。またフィリピンには信号がほとんどなく,交通ルールも曖昧であるのに加えバイクが主流な交通手段であるため交通事故による手術がとても多いこと。フィリピンでは肉を好み野菜が少ない食生活であり味が濃いことに加え運動をするのがあまり好きではない文化であり気温が高いことから心臓発作など血管系の病気が多いこと。甘いものも多く食べるため糖尿病の患者が多いこと。子供では水や食べ物がきれいではないことから生じる下痢などによる入院が多いこと。このように日本との生活習慣,気候,環境の違いから生じる主要な疾患の違いを感じました。患者を収容する場所が足りなくなったらどうするのかと伺ったところ来る患者さんを拒むことは考えられないので最悪の事態では1つのベッドに2人の患者さんを配置するとのことでした。また狂犬病予防ワクチンの接種は高価であるため犬や猫の創傷,咬傷で外来を訪れる患者さんが多く来られており,日本では見ることのできない狂犬病の治療を見学できたのは大変興味深かったです。
残りの3日間は Rural Health Unit という保健所のような施設を訪れました。外来患者さんの診察前のバイタルを取らせていただき血圧の患者さんが多いことに気づきました。また検査室を訪れ日本では機械で行われている検査(尿検査の分析など)を手動で見ることができ検査の原理を理解することができました。さらに,救急車に乗り複数のバランガイ(町)を訪れ,妊婦への破傷風の予防接種,新生児へのBCG,B型肝炎,麻疹,おたふくのワクチン接種,ポリオの経口投与を見学し手伝わせていただきました。日本と異なり近くの診療所で常に必要なワクチンの接種をすることはできず月一回の回診が新生児の定期接種の機会になっていることを学びました。さらに小学校を訪れ小学6年生の子どもたちにフィリピンで多い糖尿病と心臓発作などの血管系疾患をテーマとして取り上げて説明し予防策,初期症状を発表し栄養指導を行いました。Pinngan pinoy(フィリピンの栄養指導)を用いて実際にどのようなものを食べるべきか考えてもらいました。
全体として日本とフィリピンでは年齢別人口構成が異なっているため入院患者,外来患者とともに高齢者よりも子供,中高年が多く,病院を訪れる原因となる疾患も異なっていました。またフィリピンでは医療従事者同士が患者さんの前でも空いている時間はお喋りをして笑いあい明るい雰囲気の中で仕事をしており国民性の違いに気づかされ興味深かったです。今回医学に興味を持った原点である新興国・発展途上国の医療を見学する事ができ大変有意義な時間でした。
今回の病院見学,保健所の見学では医療設備の違いをはじめとし,日本との様々な違いに気がつきました。より多くの知識を身につけ一つの病気を患者さんに対して日本と同じ治療をしているのか,同じ薬を処方しているのかなど専門的な視野から医療の違いを観察したいです。そのため今後の大学生活では自分自身医療英語の勉強や医学の知識の強化をしたいと強く感じました。将来どのような専門性を身につけるかは決めていませんが,どのような形でも新興国・発展途上国の医療に関与したいと感じておりそのために努力していきます。